-
- <予約・問合せ>
-
077-558-6778
9:00-17:00 土・日は15:00まで
休診:祝日・お盆・年末年始
-
24時間受付
WEB予約
-
Recruitment
採用情報
-
077-558-6778
-
WEB予約
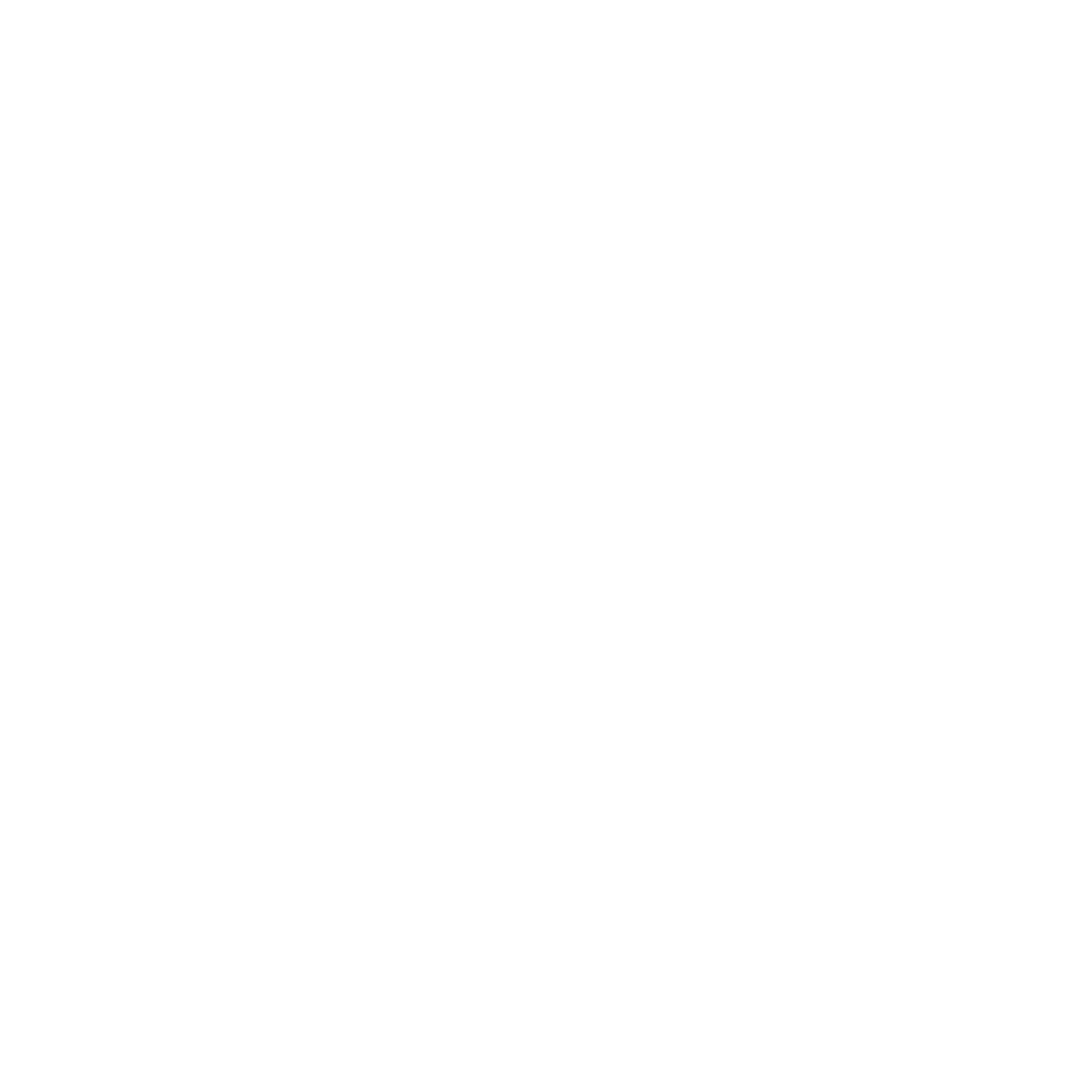
クローン病
- ホーム
- クローン病
クローン病は、主に小腸や大腸など消化管に慢性的な炎症を引き起こす疾患で、いわゆる「炎症性腸疾患(IBD)」のひとつに分類されます。日本では比較的まれな病気ですが、近年は食生活の欧米化などの影響で患者数が増加傾向にあり、若年層での発症も少なくありません。
この病気の特徴は、炎症が腸の粘膜の表層だけでなく、より深い層にまで及ぶこと、そして腸のどの部分にも不規則に炎症が現れることです。特に10代後半から30代の若年成人に多く見られる傾向があります。
はっきりとした原因は未解明ですが、免疫異常、遺伝的要素、環境因子が複合的に関与していると考えられています。
クローン病によっておこる症状
クローン病では、腸の慢性的な炎症によって様々な消化器症状が引き起こされます。特に腹痛と下痢は代表的で、多くの患者さんが繰り返し経験します。腸の狭窄や潰瘍が進行すると、便が通過しにくくなり、腹部膨満感や便秘といった症状が加わることもあります。
また、腸での栄養吸収がうまくいかなくなるため、体重減少や栄養不良、貧血といった全身症状も見られやすくなります。症状の強さや頻度には個人差があり、「活動期(炎症が強い状態)」と「寛解期(症状が落ち着いた状態)」を繰り返すのが特徴です。
さらに皮膚や関節、目など、腸以外の臓器にも炎症が波及することがあり、全身性の病気として対応が必要となります。
典型的な症例は腹痛と食事摂取不良を繰り返し、食事を取らないでいると病状がやや改善するため、病院に受診した頃にはCT検査などを行っても明確な原因が特定でき症例また一般の内視鏡検査では小腸まで観察することが困難であり、診断がつかないまま、心の病気とされ、長く本当の病状に気づかずに苦しむ方がおられます。
クローン病の検査方法
クローン病は症状だけでは他の消化器疾患と区別がつきにくいため、正確な診断にはいくつかの検査を組み合わせて行います。
まず行われるのは内視鏡検査です。大腸カメラや小腸のカプセル内視鏡によって、腸管の炎症の広がりや潰瘍の分布を詳細に確認します。クローン病特有の「敷石状病変(敷石のようにまだらに腸粘膜が残る状態)」があれば、診断の手がかりとなります。
次に**組織検査(生検)**を行い、炎症の深さや細胞の変化を顕微鏡で確認します。加えて、血液検査で炎症の程度や貧血の有無、栄養状態を把握することも不可欠です。
また、腸の狭窄や瘻孔(腸から別の部位へトンネルのようにつながる異常)を評価するため、MRIや造影CT、超音波検査などの画像診断も活用されます。
クローン病の治療
クローン病の治療は完治を目指すものではなく、炎症を抑えて寛解を維持し、再燃を防ぐことが主な目的となります。治療は患者さんの病状の程度や症状の場所、重症度によって個別に検討されます。
栄養療法が重要な柱のひとつです。腸の負担を減らすために、成分栄養剤を活用したり、低残渣(ていざんさ)食と呼ばれる消化しやすい食事にすることで、炎症の鎮静化を図る場合があります。
またまず炎症を抑えるために、5-ASA製剤や副腎皮質ステロイドが用いられます。炎症が強く再発を繰り返すような場合には、**免疫調整薬や生物学的製剤(抗TNF-α抗体など)**といった、より強力な薬が選択されることもあります。
狭窄や瘻孔がある場合には、内視鏡的処置や外科手術が必要になることもありますが、可能な限り手術を回避し、腸管を温存することが治療の基本的な考え方です。以前は治療選択肢が少なく、腸管切除を繰り返さざるおえない症例も多かったですが、最近では日々新しい薬剤が承認され、無手術期間も徐々に延長されてきています。
クローン病のフォローアップ
クローン病は長期にわたる付き合いが必要な慢性疾患です。そのため、定期的なフォローアップと生活環境の整備が非常に大切です。
治療を開始した後も、医師と相談しながら定期的な血液検査や内視鏡検査を行い、病状の再燃の兆候を早期に把握することが望まれます。病状の増悪とは別にクローン病を背景にもつ方の炎症性発癌のリスクも指摘されており、病状が比較的安定した寛解期であっても油断せず、腸管以外にも全身検査を継続してお行い、自覚症状の変化に気づく感覚を養うことも重要です。
また、ストレスや過労、喫煙は再発のリスクを高める要因とされており、日常生活の中でこれらをコントロールすることも病状管理の一環です。
食事については、患者さんごとに合う・合わないが異なるため、専門の医師や栄養士と連携しながら、自分に合った食事内容を模索する必要があります。