-
- <予約・問合せ> 完全予約制
-
077-558-6778
9:00-17:00 土・日は15:00まで
休診:祝日・お盆・年末年始
-
24時間受付
WEB予約
-
事前にかんたん
WEB問診
-
採用
情報
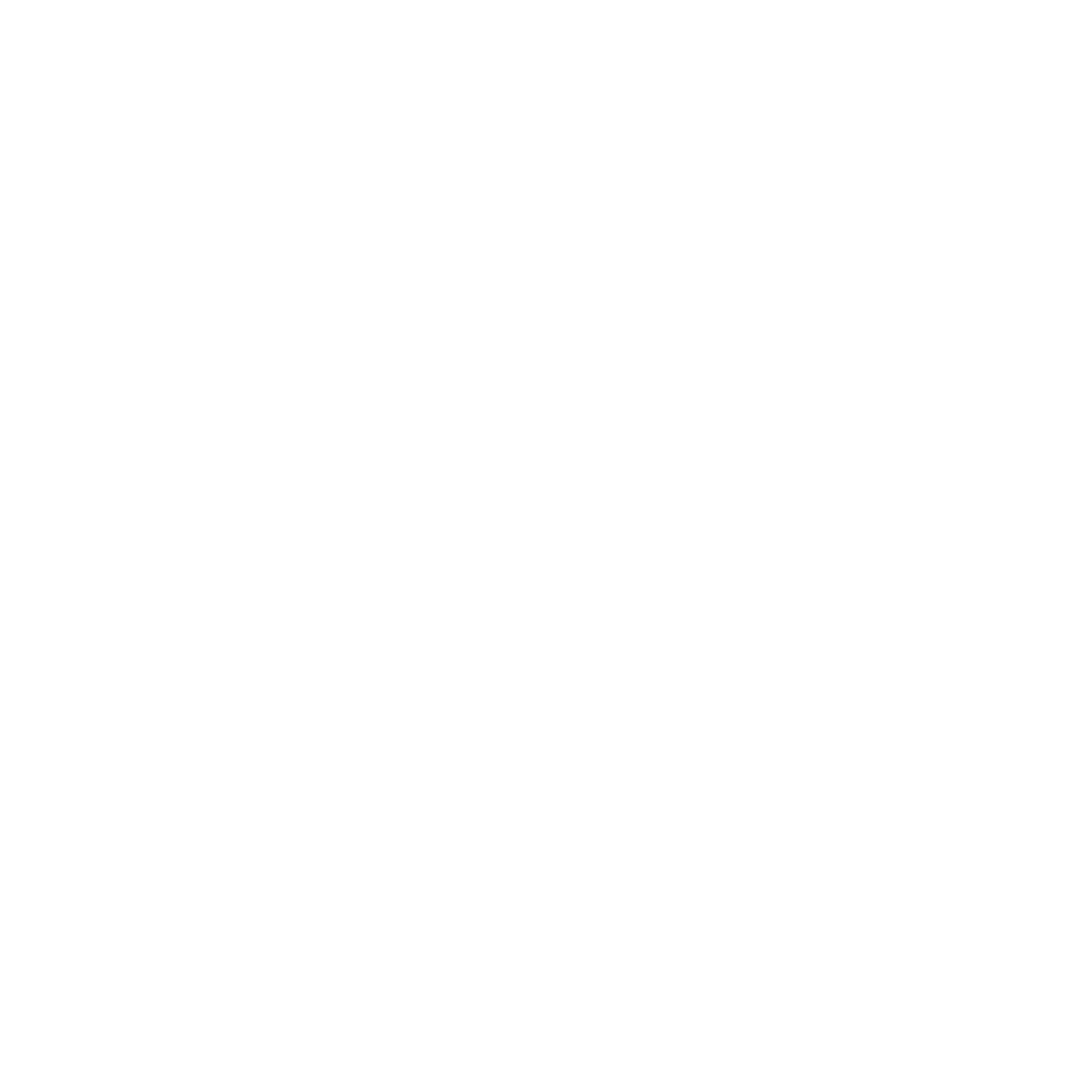
食道がん
- ホーム
- 食道がん
食道がんは、食べ物や飲み物が口から胃へと運ばれる通り道である食道に発生する悪性腫瘍です。日本における食道がんの年間罹患者数は約27,000人であり、がん全体の中では比較的頻度が低い疾患とされていますが、進行が早く予後が厳しいがんの一つとして知られています。
食道は長さ約25センチメートルの管状の臓器で、頸部、胸部、腹部の3つの部分に分けられます。食道がんの多くは胸部食道に発生し、その組織型によって扁平上皮がんと腺がんに大別されます。日本人に最も多いのは扁平上皮がんで、全体の約90%を占めています。
扁平上皮がん
口の中や舌、喉(咽頭)から食道は扁平上皮に覆われています。その他にも肛門、子宮頸部、外陰部、膣、皮膚が扁平上皮と呼ばれる組織で全て覆われております。その扁平上皮から発生するがんが扁平上皮癌です。扁平上皮がんの特徴は通常の光を用いた内視鏡ではやや赤みが目立つだけですが、NBI (arrow Band Imaging 狭帯域光観察)の条件で観察するとブラウン色に見えます。そのため扁平上皮がんを早期に発見するためにはこのNBIまたはそれに準ずる機能を持った内視鏡で胃内視鏡検査を受けて頂くことが必要です。
腺がん
西欧諸国では食道腺がんが一般的な食道がんになってきています。以前は西欧諸国でも扁平上皮がんが食道がんのほとんどを占めていましたが、近年急激に診断される腺がんが増え、アメリカでは60%以上の食道がんが腺がんと言われています。この腺がんは食道と胃の境界(接合部)にできることが多く、腺がんの発生母地としてはバレット食道が有名です。バレット食道とは食道下部の扁平上皮が、胃の粘膜に置き換えられている状態です。バレット食道の発生要因は逆流性食道炎(GERD)、中心性肥満、食道腺がんやバレット食道の家族歴と喫煙です。
食道がんの症状
初期症状
食道がんの初期段階では自覚症状がほとんどなく、診断が難しいことがあります。早期に現れる症状の代表例が嚥下時違和感で、食べ物や飲み物が喉や胸に引っかかるような感覚として感じられます。初期では熱い飲み物や辛い食べ物でのみ感じることも多く、日常生活への影響は軽微なため見過ごされがちです。早期発見のためには、違和感を自覚した際の早めの受診が重要です。
進行に伴う症状
食道がんが進行すると、まず嚥下困難が現れます。初期には固形物のみ飲み込みにくく、次第に柔らかい食事や水分、唾液までも飲みにくくなります。胸の中央部に刺すような痛みや重苦しい鈍痛が生じることもあり、食事時や安静時に現れる場合があります。進行に伴い、嚥下困難による食事量の減少やがん細胞による代謝変化で体重が減少します。また、反回神経浸潤による嗄声、気管・気管支への浸潤による咳や呼吸困難、食道の狭窄や出血による嘔吐・吐血なども起こることがあります。これらは進行度の指標となるため、異常を感じたら早めの受診が重要です。
食道がんの原因
食道がんの発症には複数の要因が関与しており、これらの危険因子が組み合わさることで発症リスクが高まります。日本人に多い扁平上皮がんと、近年増加傾向にある腺がんでは、危険因子が異なることが知られています。
喫煙
喫煙は食道がんの重要な危険因子で、タバコの有害物質が食道粘膜に直接作用し、がん化を促進します。喫煙者の発症リスクは非喫煙者の約3~5倍で、喫煙量や期間が長いほど高まります。禁煙すればリスクは徐々に低下し、10年以上経過すると非喫煙者に近づくと報告されています。健康維持のためにも早めの禁煙が推奨されます。
飲酒
アルコールの摂取も食道がんの重要な危険因子です。アルコールが体内で代謝される際に生成されるアセトアルデヒドが、食道の粘膜に損傷を与え、がん化を促進します。日本人の約半数は、アセトアルデヒドを分解する酵素の活性が低く、特に飲酒によるリスクが高いとされています。飲酒により赤面する方がおられますが、この方を医学上フラッシャーと表現しており、食道がんの発症リスクは同様の飲酒習慣の非フラッシャーと比較して1.5~3倍高くなるとされています。飲酒量が多いほどリスクは増加し、喫煙との併用で相乗的に高まることも知られています。
逆流性食道炎
胃酸が食道に逆流することで起こる逆流性食道炎は、特に腺がんの危険因子として重要です。慢性的な胃酸の逆流により食道の粘膜が炎症を起こし、長期間にわたって刺激を受けることで、がん化のリスクが高まります。
逆流性食道炎が長期間持続すると、食道の下部で正常な扁平上皮が円柱上皮に置き換わる「バレット食道」という状態になることがあります。バレット食道は腺がんの前がん病変と考えられており、定期的な内視鏡検査による経過観察が推奨されています。
食道がんの検査方法
食道がんの診断は、まず症状の聴取と身体診察から始まります。嚥下困難や胸部不快感の有無、症状の持続や進行の程度を詳しく確認し、喫煙歴や飲酒歴、体重減少や食事摂取量の変化など生活習慣や栄養状態も評価します。身体診察では、リンパ節の腫れや肝臓の腫大など転移を示唆する所見がないか注意深く観察します。
中心となるのは上部消化管内視鏡検査です。口から細い内視鏡を挿入し、食道や胃、十二指腸の内部を直接観察します。通常光に加え、狭帯域光観察(NBI)やブルーレーザー光観察(BLI)により微細な血管や粘膜の変化を捉え、早期がんの発見率が向上します。異常が確認されると生検で病変の組織を採取し、がんの有無や組織型を確定します。生検は外来で行える場合が多く、痛みはほとんどありません。
がんの進行度や転移の有無を評価するため、CT検査やMRI検査、PET検査などが行われます。CTは食道壁の浸潤やリンパ節転移、肝臓や肺などの遠隔転移の確認に有用です。MRIは壁の層構造や周囲臓器への浸潤、肝臓転移の詳細な評価に優れます。PET検査ではがん細胞の代謝活性を画像化し、小さな転移巣の発見に役立ちます。
超音波内視鏡検査(EUS)では内側から超音波で壁の層構造を観察し、がんの深達度を正確に評価できます。心臓や大血管近くの病変では経胸壁心エコーで影響を確認します。さらに、呼吸機能や心機能検査で手術や化学療法に耐えられる体力を確認し、血液検査で栄養状態を評価することも重要です。これらを総合して最適な治療方針が決定されます。
食道がんの治療
食道がんの治療方針は、がんの進行度(ステージ)、患者さんの全身状態、年齢、合併症の有無などを総合的に判断して決定されます。内科医、外科医、放射線治療医、薬物療法専門医などによる多職種カンファレンス(キャンサーボード)で検討されることが一般的です。治療は根治を目指す根治的治療と、症状緩和を目的とする緩和的治療に大別されます。
内視鏡治療
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)は早期食道がんに対する低侵襲な治療法で、病変部の粘膜を一括切除します。適応は粘膜内にとどまり、リンパ節転移の可能性が低い場合です。全身麻酔下で行い、入院は数日間です。
外科治療
食道切除術は根治的治療の代表で、がんの位置や進行度に応じて胸部食道切除術、食道亜全摘術、食道全摘術などが選択されます。切除後は胃や結腸を用いて食道を再建します。
鏡視下手術は創が小さく、術後の痛みが軽減され回復が早い利点があります。術前には栄養改善や呼吸機能向上、口腔ケアを行い、術後は呼吸・循環・感染・栄養管理を含む集学的管理が重要です。
化学療法
術前化学療法は手術可能な進行食道がんに行われ、がんを縮小し微小転移を制御します。シスプラチンと5-FU、またはDCF療法などが用いられます。
化学放射線療法は手術適応外や希望による場合に行われ、化学療法と放射線療法の相乗効果で治療効果が高まります。
緩和的化学療法は進行・再発食道がんで症状緩和と延命を目的に実施され、新しい免疫チェックポイント阻害剤やタキサン系薬剤も選択肢に含まれます。
放射線治療
根治的放射線治療は手術困難な早期食道がんに対して行われます。
術後放射線治療は再発リスクが高い場合に局所再発を抑制します。
緩和的放射線治療は骨転移や食道狭窄による痛みや嚥下困難の改善を目的に短期間で行われます。
食道がんの予後
食道がんの予後は、診断時の進行度によって大きく異なります。早期(ステージ0~I)では5年生存率が90%以上と良好ですが、進行例(III~IV)では20~40%程度にとどまります。深達度やリンパ節転移、遠隔転移、全身状態などが予後を左右します。治療後は再発の早期発見を目的に、血液・CT・内視鏡検査などを定期的に行います。治療後2年間は3~4か月ごと、3~5年目は半年ごと、以降は年1回の経過観察が一般的です。嚥下困難や胸痛などの再発症状があれば早めの受診が大切です。